漢方薬処方の基本原則
- 漢方を扱っている製薬会社の担当者への確認によると、漢方薬の併用は一般的には「2種類まで」が推奨されます。
- これは、漢方治療に精通していない一般医師が安全に使用するための目安であり、熟練した東洋医学専門医は症状に応じて3処方以上を組み合わせる場合もあります。
.jpeg)
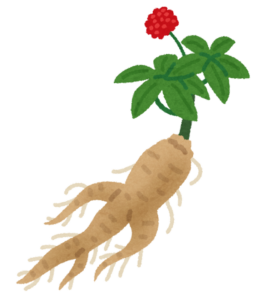
漢方処方時に成分の重複に注意を!
漢方薬処方の原則:なぜ2処方までか?
生薬成分の重複による副作用リスク回避
例:甘草(カンゾウ)や麻黄(マオウ)が複数処方に含まれ、合計量が過剰になる。
成分量が増えると、副作用(偽アルドステロン症や交感神経刺激症状)が顕在化する可能性が高まります。
薬効評価を明確にするため
3処方以上を同時に開始すると、どの処方が有効か、または副作用を起こしているか判断が困難になります。
患者服薬アドヒアランスの維持
漢方薬は1日2~3回服用が必要なため、処方数が多いと飲み忘れや誤服用が増えます。
注意すべき代表的な生薬と副作用
甘草(カンゾウ)
主成分:グリチルリチン
過剰服用で偽アルドステロン症を引き起こす可能性
症状:
高血圧
浮腫
低カリウム血症(筋力低下、不整脈)
厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル」では、1日2.5g以上の長期投与でリスクが上昇するとされ、腎機能障害・高血圧・電解質異常がある患者では特に注意が必要と記載されています。
麻黄(マオウ)
含有成分:エフェドリン類
中枢・末梢交感神経刺激作用により副作用が出現
症状:
不眠、興奮、動悸、発汗
高血圧、頻脈
気管支拡張薬や交感神経刺激薬との併用は特に注意。
その他注意すべき生薬
| 生薬 | 主な副作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 附子(ぶし) | しびれ、悪心、心室性不整脈 | 過剰投与で心毒性 |
| 大黄(だいおう) | 下痢、腹痛、低カリウム血症 | 下剤成分との併用注意 |
医療者が行うべき管理のポイント
処方前に成分量を確認する
甘草や麻黄を含む処方は、添付文書で1日あたりの含有量を確認する。
特に2処方以上併用する場合は合算する。
患者背景をチェックする
高血圧、腎機能障害、心疾患、電解質異常がある患者はリスクが高い。
高齢者は副作用発現が顕著になりやすいため慎重に投与。
モニタリング
血圧、浮腫の有無、血清カリウム値を定期的に測定。
特に甘草併用時は低カリウム血症の早期発見が重要。
処方のステップアップ
まず単剤で開始し、効果が不十分なら2処方目を追加。
症状改善後は中止または減量を検討する。
含有量の目安
1. 麻黄(マオウ)の1日含有量目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要成分 | エフェドリン類(交感神経刺激作用) |
| 1日あたりの目安 | 5.0 g(生薬量)以下 |
| 安全域 | 4.5〜5.0 gまでが一般的な最大量 |
| 主な含有処方 | 麻黄湯、小青竜湯、葛根湯、防風通聖散など |
| 注意点 | 交感神経刺激作用により、不眠、動悸、血圧上昇などが出やすい。高血圧・心疾患・甲状腺機能亢進症の患者では慎重投与。 |
例:ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
1日7.5g中に「麻黄 3.0g」含有
→ 併用で麻黄が重複すると合計5.0gを超えないように管理する必要あり
2. 甘草(カンゾウ)の1日含有量目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要成分 | グリチルリチン(偽アルドステロン症の原因成分) |
| 1日あたりの目安 | 2.5 g(生薬量)以下 |
| 安全域 | 1.5〜2.5 gまで |
| 主な含有処方 | 小青竜湯、葛根湯、抑肝散、補中益気湯、半夏厚朴湯など多数 |
| 注意点 | 長期服用・高齢者・腎機能障害・利尿薬併用でリスク増大。低カリウム血症、高血圧、浮腫、不整脈に注意。 |
例:ツムラ抑肝散エキス顆粒
1日7.5g中に「甘草 1.5g」含有
→ 2処方併用時、甘草の合計が2.5gを超えると副作用リスク上昇
漢方薬処方の原則:文献・ガイドラインからの推奨
嶋田豊ら「注意しておきたい漢方診療上の副作用」では、
「麻黄による興奮、不眠、交感神経刺激作用」「甘草による偽アルドステロン症」が特に注意すべき副作用として挙げられています。厚生労働省の「重篤副作用疾患別対応マニュアル(第二版)」では、グリチルリチン含有製剤の長期使用に伴う偽アルドステロン症の記載があり、患者背景や併用薬を考慮した適正使用が求められています。
参考文献
嶋田豊. 注意しておきたい漢方診療上の副作用. 川・和漢診療関係. 2020. [CiNii Research]
厚生労働省, PMDA. 重篤副作用疾患別対応マニュアル(第二版). 2021.
まとめ
漢方薬は原則2処方までが推奨され、重複する生薬による副作用リスクを避けることが重要。
特に甘草と麻黄は含有量の合算管理を徹底する。
患者背景を確認し、血圧や血清カリウム値を定期的にモニタリングすることで副作用を早期発見できる。
安全で効果的な漢方治療には、西洋医学と東洋医学双方の視点が不可欠です。
.jpeg)