はじめに
-
経口避妊薬(OC: Oral Contraceptives)や低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP)は、避妊や月経困難症、子宮内膜症などの治療目的で広く使用されています。
しかし、これらの薬剤には血栓症リスクを増加させる作用があることが知られています。 -
特に全身麻酔を伴う手術では、麻酔そのものに加えて手術後の安静、脱水、炎症反応が重なり、深部静脈血栓症(DVT)や肺塞栓症(PE)といった重篤な合併症が発生しやすくなります。
そのため、ピル服薬中の患者が手術を受ける場合、術前にピルを休薬するかどうかは非常に重要な周術期管理のポイントとなります。 -
かつては「手術の4週間前にはピルを中止する」というルールが広く用いられてきましたが、手術内容や麻酔方法、患者背景によっては休薬が不要な場合もあります。
最新のガイドラインでは、血栓症リスクを正確に評価したうえで個別に判断することが推奨されています。 -
本記事では、
-
ピルと血栓症の関係
-
全身麻酔前の休薬タイミング
-
術後再開の目安
-
患者指導のポイント
を整理し、臨床現場ですぐに活用できる知識を解説します。
患者安全を守るためのピル管理を、医療者として改めて見直しましょう。 -
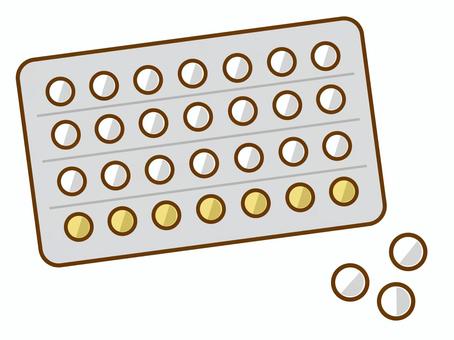
ピル
ピルと血栓症リスク
- ピルには、エストロゲンとプロゲスチンが含まれています。特にエストロゲンは血液凝固因子を増加させ、血栓症リスクを上昇させます。
服薬者では、非服薬者と比べて2〜4倍の静脈血栓症リスクがあるとされています。
高リスクとなる背景
35歳以上
喫煙
肥満(BMI≧30)
過去の血栓症歴
遺伝性血栓性素因(例:Protein S欠損症)
- 全身麻酔下の手術では、麻酔薬による血管拡張や血流停滞、長時間の臥床が重なり、血栓形成がさらに促進されます。
- このため、ピル服薬+全身麻酔+長時間臥床という条件が揃うと血栓症発症リスクが一気に上昇します。
ガイドラインに基づく休薬タイミング
1. 手術前
-
日本麻酔科学会・日本産科婦人科学会では、原則として手術の4週間前に休薬開始を推奨。
-
休薬が間に合わない場合は、周術期にDVT予防策を強化する(弾性ストッキング、間欠的空気圧迫装置、抗凝固薬など)。
-
日帰り手術や短時間手術(眼科や形成外科など)では、休薬不要な場合もあります。
2. 術後再開時期
-
術後、歩行再開後2週間程度経過してから再開するのが目安です。
-
再開直後は下肢腫脹や疼痛、呼吸困難など血栓症の兆候に注意。
3. 緊急手術の場合
-
術前に休薬できないまま手術が行われるケースでは、以下が重要です。
-
周術期に抗凝固療法やDVT予防器具を使用
-
早期離床を促す
-
高リスク患者では集中管理下でのモニタリング
-
.jpeg)
実際の周術期管理フロー
| タイミング | 医療者が行うべきこと |
|---|---|
| 手術決定後 | ピル服薬の有無を確認、休薬指導 |
| 術前4週間 | 休薬開始 |
| 手術前日 | DVT予防策を確認 |
| 術後 | 早期離床、弾性ストッキング、抗凝固薬 |
| 術後2週間後 | 血栓症症状がなければピル再開 |
患者指導のポイント
-
血栓症徴候への注意喚起
-
下肢腫脹・疼痛、呼吸困難、胸痛があればすぐに受診するよう指導。
-
まとめ
-
ピル服薬中の患者が全身麻酔を受ける場合は、原則として4週間前から休薬。
-
術後は歩行再開後2週間程度経過してから再開。
-
緊急手術では抗凝固療法やDVT予防を強化する。
-
患者には避妊指導と血栓症症状への注意喚起を徹底することが重要。
参考文献
-
日本麻酔科学会 周術期管理ガイドライン2023
-
日本産科婦人科学会 OC・LEPガイドライン2022
-
Heit JA. Venous thromboembolism epidemiology: implications for prevention and management. Semin Thromb Hemost. 2002;28 Suppl 2:3-13.
.jpeg)