はじめに
国際学会を主催したり、海外からの留学生を受け入れたりする際、意外と問題になりやすいのが食事の宗教的・思想的制限です。
例えば、イスラム教徒のハラル食、ヒンドゥー教徒の牛肉禁止、そして近年増えているヴィーガン・ベジタリアン対応など、日本ではまだ馴染みが薄いケースも多く、事前準備が欠かせません。
誤った食事提供は、参加者や患者さんとの信頼関係を損なうリスクがあるため、医療者や学会運営側が基本知識を持つことが重要です。

イスラム教徒は豚肉やアルコールを避ける必要がある。
各宗教ごとの食べられないもの一覧
| 宗教 / 思想 | 食べられないもの | 補足 |
|---|---|---|
| イスラム教(ムスリム) | 豚肉・豚由来成分、アルコール | 肉はハラル認証が必要 |
| ユダヤ教(コーシャ) | 豚肉、ウサギ、貝類、肉と乳製品の同時摂取NG | コーシャ認証必須 |
| ヒンドゥー教 | 牛肉(神聖視される) | 地域により完全菜食主義者も多い |
| 仏教(厳格派) | 肉類、魚、五葷(ニンニク、ネギ、ニラ、ラッキョウ、タマネギ) | 精進料理が基本 |
| キリスト教(カトリック) | 四旬節中は肉を避ける日がある | 個人差が大きい |
| ベジタリアン | 肉類、魚介類 | 卵・乳製品は可の場合がある(ラクト・オボなど) |
| ヴィーガン | 肉、魚介類、卵、乳製品、蜂蜜 | 完全植物性食品のみ |
.jpeg)
ハラル食とは?
ハラルの意味
- ハラル(Halal)とは、アラビア語で「許されたもの」という意味で、イスラム教の教えに基づく食事規定です。
逆に「禁止されているもの」はハラーム(Haram)と呼ばれます。 - 特に肉に関しては、食べられる動物の種類だけでなく、屠殺方法が非常に重要です。
ハラルにおける屠殺方法の基準
- イスラム法では、以下の条件を満たしていなければ、肉はハラルと認められません。
アラー(神)の名を唱える
屠殺時に「ビスミッラー、アッラーフ・アクバル(神の御名と偉大さを称える言葉)」を唱えます。屠殺者はイスラム教徒または啓典の民であること
啓典の民=ユダヤ教徒やキリスト教徒も含まれます。動物を苦しませない
屠殺前に動物を優しく扱い、ストレスを最小限に。
よく研いだ鋭利なナイフで、一度に喉を切り、気管・食道・頸動脈・頸静脈を迅速に切断します。
血を完全に抜く
体内に血液を残さないよう放血処理が必要です。
ハラーム(禁止される例)
以下の場合はハラルと認められません。
屠殺時にアラーの名を唱えない
殴打や感電で殺された動物
自然死した動物
血を抜かずに調理した肉
豚肉および豚由来成分(ゼラチンなど)
まとめ:ハラル肉のポイント
- ハラル肉は、単に「豚肉を使っていない」というだけでは不十分です。
- 屠殺方法が規定通りであることが必須であり、調理器具や調味料もハラル専用で管理される必要があります。
- 国際学会や病院食でハラル対応をする際は、必ずハラル認証を受けた業者を選ぶことが大切です。
東京で手配できるハラル対応弁当店(国際学会向け)
1. 東京ハラルデリ&カフェ Tokyo Halal Deli & Cafe
特徴: ムスリム監修、完全ハラル対応
価格帯: 1,600円〜
2. HALAL DELI
特徴: 学会やイベント向け大量注文可能
価格帯: 2,000円〜
3.人形町今半おもてなし弁当サイト
特徴: ベジタリアンのための弁当あり
価格帯: 2,000円〜
- Web: https://bento.imahan.com/products/detail/119748
4.ごちクル
特徴: ヴィーガン・ハラール・ベジタリアン弁当
価格帯: 1,000円〜
- Web: https://gochikuru.com/feature/style/?srsltid=AfmBOorHx3dSPPl5ruX99GykDLbNBl8wiecdhcmn4CCB6M5Bc_qZkTmA
学会運営での実践ポイント
事前アンケートで宗教食の希望を確認
→ イスラム教、ヒンドゥー教など具体的に記載欄を設ける料理には必ず英語と日本語で表示
"Contains Pork" / "No Pork"
"Halal Certified"
飲み物にも注意
→ アルコール入りデザートや調味料を避ける
まとめ
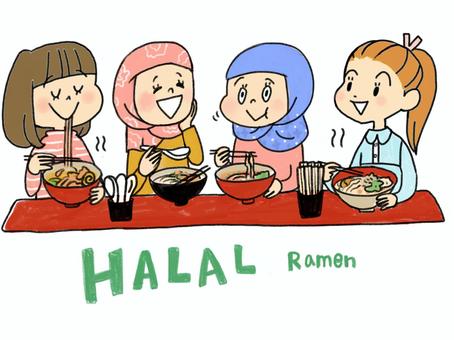
参加者の宗教や食事に配慮して学会の成功を
国際学会や留学生との交流では、食事制限への配慮が信頼関係を築く第一歩です。
特にハラル対応は日本ではまだ普及途上のため、早めに専門業者と連携しましょう。
適切な食事対応が、学会運営の成功につながります。